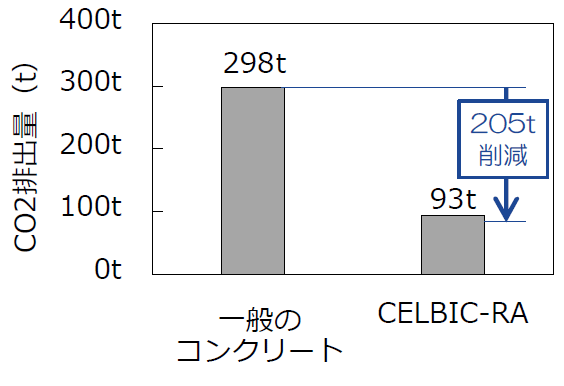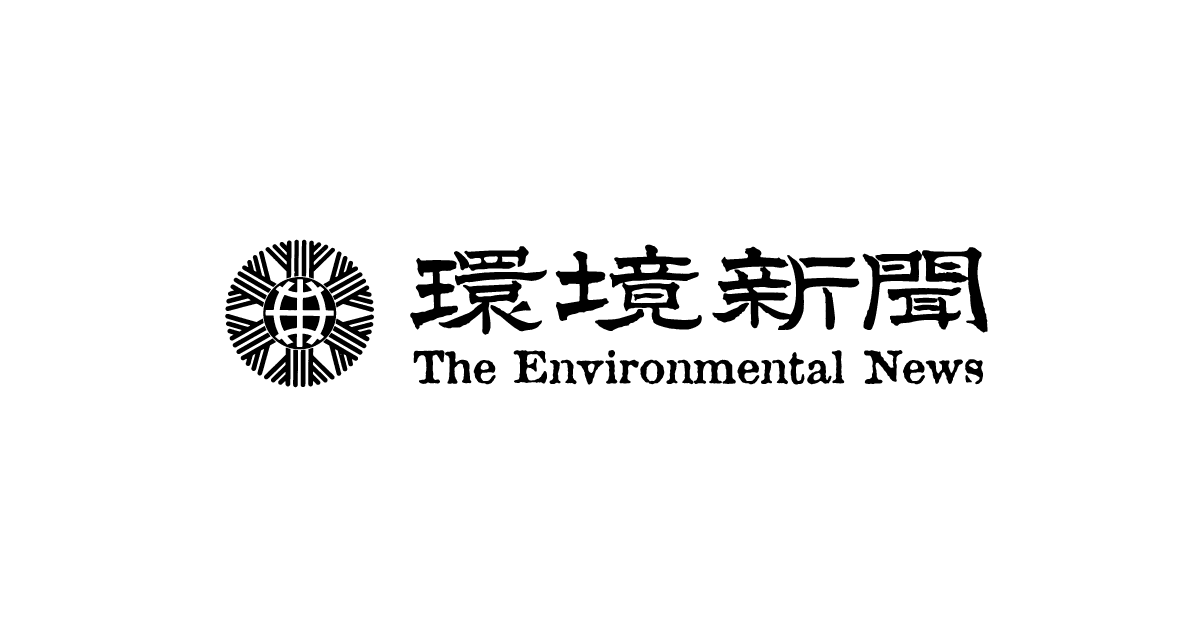生物学×環境~大学の研究室より~2‐(27) 猛暑の大阪と京都で感じた木に対する想い
大阪夢洲で開催中の万博に行きました。夏休みが終わった直後の平日でしたがすごい人出で、パビリオンも多くは見ることができませんでしたが、会場に入ってシンボルである大屋根リングに感銘を受けました。見上げた時の存在感は素晴らしかった。現代でもこれほど大きな木造建造物ができるのだと感銘を受けました。さらにリングの上に上がると海風のせいもあり涼しく感じました。
さて東京に戻る予定にしていた日は台風15号が東進し東海道新幹線のダイヤをかき乱していました。次の日予定もない私用で出かけましたので、ならばその日無理に東京まで戻らずに京都に行こうと考え、東本願寺、東寺にお参りしました。すると期せずして木という素材の素晴らしさについて思いがけず大発見をした気分になることができました。
門、御堂や塔といった建物、仏像も全て木造です。京都には何百年という時間が経過した木造建築、仏像が多くあります。ただそれらも作られてすぐは、私が万博で見てきた大屋根リングのように原木に近いはずです。しかしそこに至るまででもまず原木自体が百年単位の成長の結果で生まれているのです。切り出されて材となり、宮大工、仏師の手を経て新たな価値を含んだものへと変化する。素晴らしい人類の成せる術です。そうしてできた建築、仏像がさらにそれ以降数百年もの間、人々にインパクトを与え続けることができるのです。さらに経年変化を重ね、素晴らしい新たな2度目の人生ならぬ、〝木〟生を歩んでいるのだと思ったのです。
お堂も天井が高く作られ、昼間でも中を歩いていると風が通り、涼しさを感じることができ、あたかも歴史の風に癒されるような不思議な感覚を味わいました。古人の知恵があるのでしょう。
平安時代には現代ほどではないにしても、30℃を超える真夏日が多かったと考えられています。そこで多くの家屋が寝殿造りで壁がなく吹き抜けにして、風通しをよくして生活をしていたようです。その遺産としての涼感を今日お堂で感じることができたのです。
さて、このように人間の手によって植物の体であった木材を利用する術が継承されていることに安心した一方、植物として生きている木に対して、この夏のような猛暑や旱魃がどのように影響するのか気になります。
雨が少ない時期が長いと、高温以上に木の成長に悪影響が出るという予想があります。高温で水が不足すると、葉からの水分の蒸散作用を抑えるため、光合成もいかなくなり、成長が鈍り、年輪も幅も狭くなるのではないかという予想です。
木の年輪は、幹の最外層に近いところに形成層という分裂組織があり、そこから分裂する細胞が多い夏の時期には細胞が良く増えて白い部分が、それに対して秋から冬には分裂が鈍るために年輪の筋に相当する部分ができ、年輪が形成されます。
この夏の時期、白い部分を作る分裂に支障をきたしている危惧があるわけです。実際のところは分かりませんが、多くの木がこの猛暑の中でもなんとか順調な成長を続け、今後も人間社会への良質な木材が提供されていくことを願わずにはおれません。
東京大学名誉教授 渡邊 雄一郎
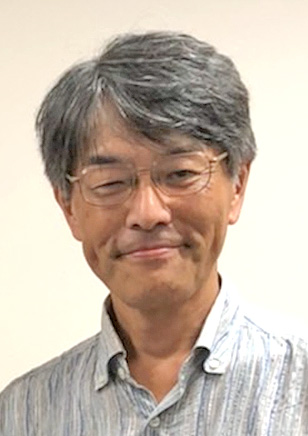


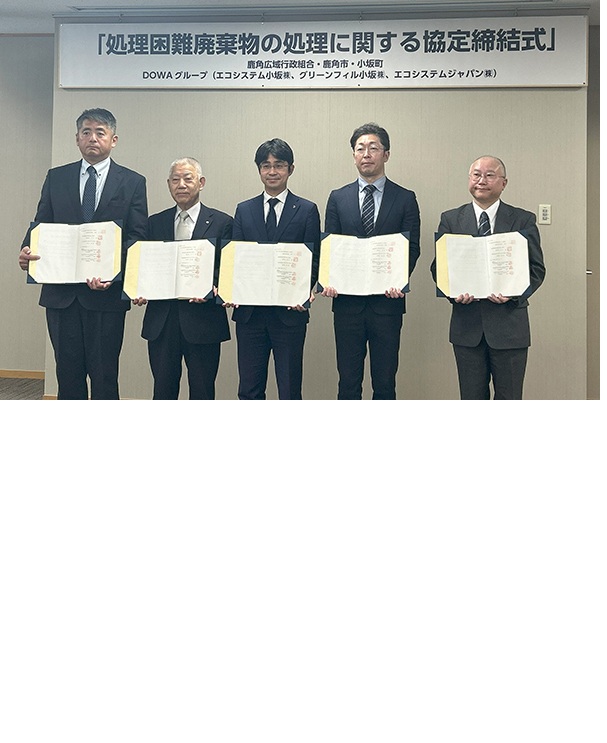
![液化水素ポンプ運転試験の様子_ [酉島製作所] 超電導モータで発熱なし 液化水素基地用 の「大流量ポンプ」を受注](https://www.kankyo-news.co.jp/uploads/2026/02/12/CJ8hr1CgotwLnJnO5XJRknSUGdc5ygzbVIWJOJQI.jpg)