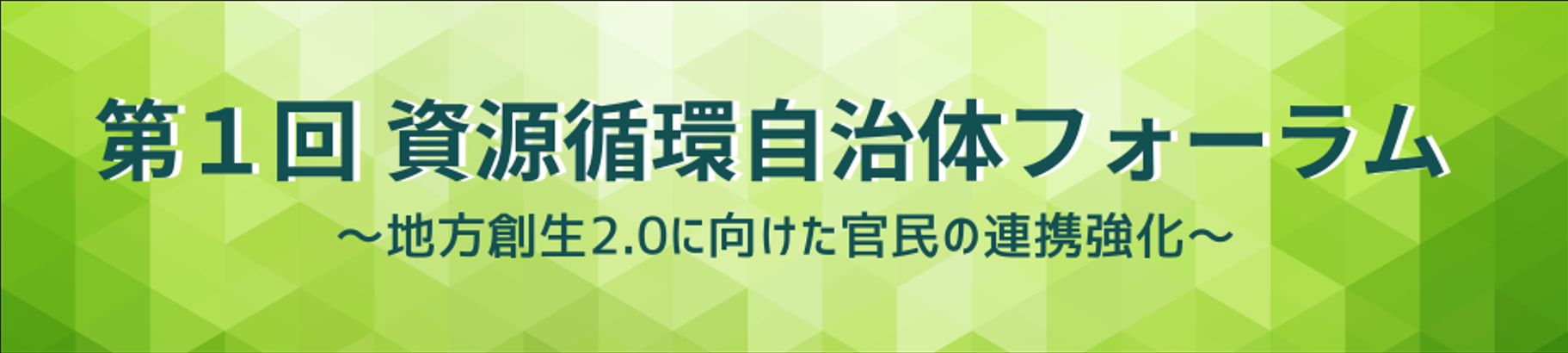2025年 我が社の環境ビジネス戦略 アンカーネットワークサービス 代表取締役 碇 隆司 氏 LCMのサービス提供で負担軽減を訴求
Windows10のサポート終了見据え、新事業所を開設
――昨年を振り返って。
昨年より新たに、PCなどのIT資産の調達から運用・保守、廃棄までの全プロセスを代行するLCM(Life Cycle Mana gement)サービスの提案を進めてきた。
また、2025年10月にサポートが終了するWindows10対策に向けてPCの入れ替え、アップデート、旧PCからのデータ移行などPCリサイクル業務の対応や、新事業所の開設に向けた準備などに向け、当社の取り組みを円滑に進めるための地盤を固める一年となった。

――LCMのメリットは。
LCMを活用する最大のメリットは「主業務に専念できること」。
DXの進展に伴い企業の負担となっている、IT機器の選定、キッティング(導入設計・計画)、運用(ヘルプデスク、修理・増設など)、廃棄(引き取り廃棄、データ消去)などをトータルに運用業務代行することで、主業務への注力を可能とし、経費の削減と負担軽減を可能にする。
本サービスの具体的な特徴としては、IT端末の導入から運用・廃棄までのワンストップサポート、各メーカーのPC、スマートフォン、タブレットなどに対応するマルチデバイス・マルチベンダー対応、消耗品の購入代行や手順書作成など、個別の要望への柔軟な対応、リスクを伴うPC廃棄時におけるデータの完全消去のノウハウや第三者のチェックを受けた高度なセキュア廃棄サービスの提供、細分化したリサイクルによる高額買取、販売代行、MS認定再生PC、リユースPCレンタルなどによる最良のIT環境とコストパフォーマンスの提供となっている。
――導入実績は。
サービスをリリースして1年ほどで、導入件数はフルサービスの導入事例で3件、部分的なサービス提供で10件程度となっている。多くの相談や問い合わせも受けており、導入実績の拡大に手ごたえを感じている。
――Windows10のサポート終了への対応は。
今年10月のWindows10のサポート終了に伴う対策や、児童・生徒向けに1人1台の端末配布と通信環境を整える「GIGAスクール構想」の対応拡大を見据え、1月に沖縄と埼玉県の新狭山、春に北海道安平町に新事業所を開設し、中古PCのリユース・リサイクル業務を強化する。
――人材育成と体制強化に向けて。
現在、アンカーネットワークサービスで206人(24年6月時点)、ICT機器の解体を軸とした中間処理施設の運営、産業廃棄物のリサイクル・リリースを行う、アンカーリサイクルポート(20年に富士通化成リサイクルの全株式を取得して設立)で約70人の体制だが、昨年新たに採用担当業務の専門部署を設け、新たな人材の確保に向けて取り組んでいる。
同時に、社員のスキルアップと企業信用度の向上を目指して、ITAD認定事業者資格の取得の奨励と受験料のサポートなどを推進している。
同資格は、IT(情報関連機器)、Asset(資産)、 Disposition(廃棄・処分・除却)に関わる業界の発展促進を目指す「日本ITAD協会」が良質なリユース品(情報機器)の認知度の向上と流通促進のために、情報機器のリユース品の取り扱いに適切な対応をしている事業者を認定する資格だ。
当社では、24年10月に行われた第1回目の認定試験で30人弱の資格取得者の認定を受けた。今後も、グループ会社を含めた全社員の資格取得を目指してサポート体制を強化し、企業価値の向上に努めていく。
――障がい者就労支援事業について。
当社は93年の創業時より「万人万物共存共生」を理念に掲げ、「社会循環品である物の命を、その与えられた役割を最後まで全うできるよう永らえさせる」ことを目指してきた。 「何かの役に立つために、母なる地球から作られた物を、おなじ命の尊厳をもって守っていくこと、社会循環品として役立てていくことは人としての責務であり、それが私達の存在価値である」と考えている。
そうした企業理念のもと「共感共創」社会を目指して、今後も障がい者就労支援事業と共に、発展させていきたい。
――今年の予定や抱負は。
このほど千葉県産業資源循環協会から当社の取り組みを評価いただき、「千葉県知事賞」を受賞することとなった。1月16日の「第24回千葉県廃棄物適正処理推進大会」で授賞式を控えている。
今年も「現世も来世もモノが輝ける仕組み」を目指し、「セカンド・マーケットのある全ての物に資源資産管理番号をつけて、誕生から最後の無害化処理まで、適切に一元管理したい」という夢の実現に向け、さらなる成長と発展を図っていく。

![[AD]BitNavigator_850_150](https://www.kankyo-news.co.jp/uploads/2026/02/17/rDUhxjfMQSzbhbshHqyA1FTfIUpHL4M0kLVTi6Ru.jpg)