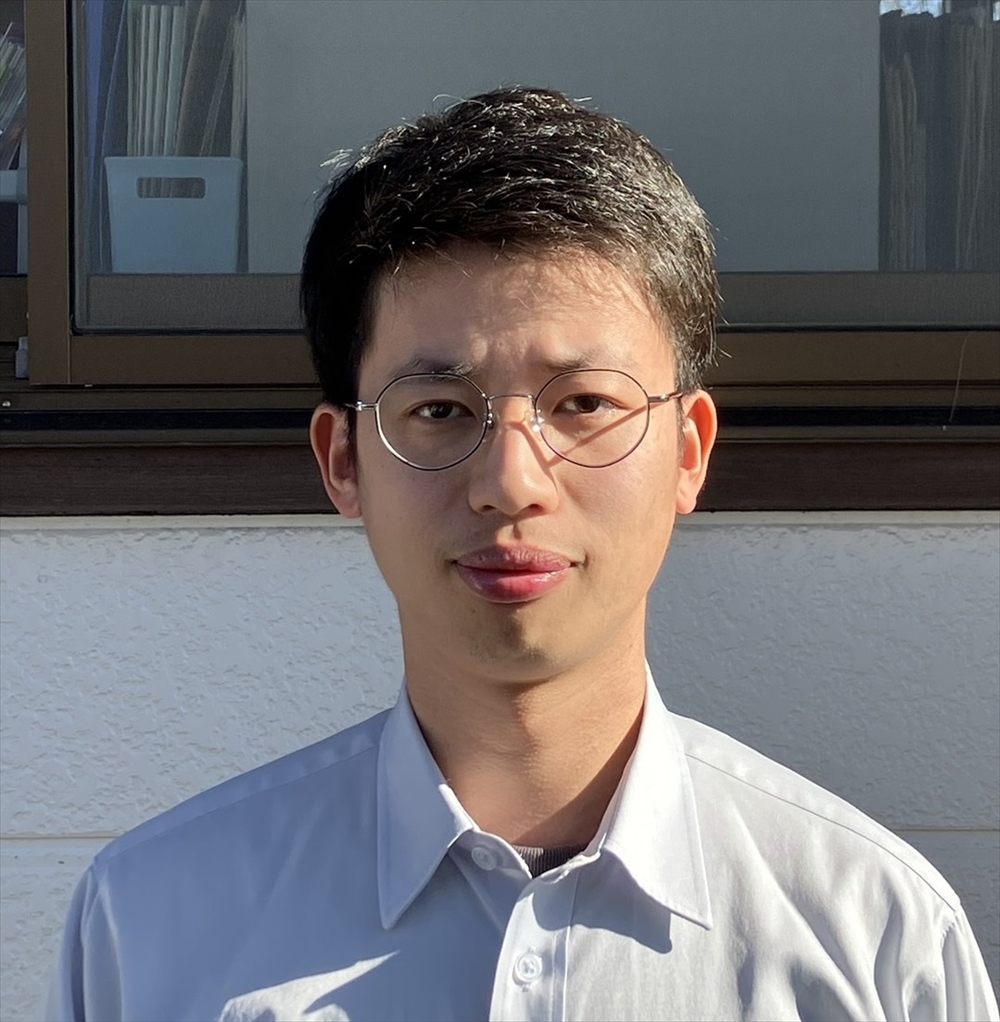リスク社会と地域づくり(22) 岩手大学農学部教授 山本 信次 元岩手大学農学部 長澤 亮太
岩手県におけるジビエ起業の成功要因と原発事故影響
野生鳥獣被害の増加とジビエ利用
2021年度の野生鳥獣による農作物被害額中シカは4割を占め、対策として行政は補助を通じて捕獲を支援している。結果、全国の捕獲数は20年度67万頭を超えたが、被害の拡大は収まらない。公費を原資とした捕獲報奨金によるインセンティブ付与には限界があることから、自律的にシカ問題に対応できる仕組みとしてジビエ利用が期待されている。しかし捕獲されたシカの利用は21年度時点で13%と低調である。捕獲されたシカの多くは埋土や焼却など経費のかかる形で処理され、二重の意味でもったいない状況にある。
岩手県におけるシカ対策と原発事故
岩手県では11年度2千頭程度だった捕獲数が20年度には2万頭まで増加し、通常なら資源としての利用にも期待がかかる。しかし東京電力福島第1原子力発電所事故の影響により、県内で捕獲されたシカ肉から基準値を超える放射性物質が検出され、12年7月に出荷制限指示が出された。以後、県内で捕獲されたシカは販売が不可能となり、法的に禁止ではないハンターの自家消費分を除き、廃棄処理が不可避となった。この後も捕獲数は維持されるが、それは捕獲数減少を懸念した県による県猟友会への捕獲委託や報奨金が捕獲意欲の減退を防いだものであり、公的負担の拡大とジビエ利用制限という「視えない被害」が今も残る。
ジビエ利用に向けた取り組み
こうした中で20年4月、大槌町に新設された食肉処理加工施設(以下、加工施設)が受け入れる地元で捕獲されたシカに限り、全頭検査を条件に出荷制限が一部解除された。運営者である「MOMIJI株式会社」は創立以降、県内外に年間300頭のシカ肉を流通させ、通販サイトでは商品が売り切れることも多い優良企業である。地元出身の船乗りだった経営者K氏は、親族の被災を機に地元への定着を決意する。その折、地域課題となっていたシカ害対策に取り組むべく狩猟免許を取得し、有害駆除に参画した。その中で単に駆除するのでなく、命あるシカを価値のあるものとして扱いたいと感じ、シカを美味しく食べるための取り組みに関心を移していった。そして復興推進隊の移住者や猟友会、大槌町役場、商工会などと協力し、大槌ジビエ勉強会を立ち上げ、被害軽減の程度、シカ肉の食肉利用方法、ジビエによる町おこし等について議論や視察を重ねた。
ここで形成されたネットワークがのちの起業に欠かせない社会関係資本となった。
また全国視察の中で、捕獲から解体まで高品質なシカ肉を得られるよう工夫を重ねた大槌のシカはどこよりも美味しいと感じ、それこそが顧客獲得の鍵との気付きを得る。そして高品質なシカ肉を提供しうる体制を持つ自分達であれば、出荷制限を解除できればビジネスとして成立するという確信から起業を実現させた。
出荷制限解除に向けた取り組み
制限解除には出荷検査方針を整え、知事から総理大臣への申請が必要となる。すなわち制限解除を受けるのは町だが申請は県が行う。そのため制限解除のための具体的準備は町役場とMOMIJIが行い、その後、町役場が県庁と相談し、その上で県庁が環境省と交渉するという間接的な手順となる。解除申請には放射性物質検査体制、処理施設の計画等が必要であり、これらを実施できる処理施設は食品加工のみならず出荷制限解除のためにも必置となる。
通常、ジビエを推進する人材育成および需要拡大につながる事業には農林水産省の鳥獣被害防止総合対策交付金が受領可能である。しかし事前の問い合わせに対し「交付金を利用したビジネスには持続性が必要であり、出荷制限のかかる大槌町では持続性に信頼が持てず、現時点では交付金は利用できない。出荷制限を一部解除し、持続性が確認できれば交付金を交付する」との回答があった。処理施設は出荷検査体制に含まれるため出荷制限一部解除申請に不可欠であり、一般には交付金を用いて建設される。大槌町では交付金と制限解除、処理施設建設をめぐって袋小路に追い込まれた。
この打開に向けたK氏の判断は「交付金を利用せず、自身が融資を受けて建設費用を賄う」であった。しかも、この時点では処理施設が完成しても出荷制限の一部解除が承認される保証はなかった。こうしたK氏の覚悟ある決断をみた関係者は「地域課題解決を一人に負わせてはいけない」と感じ、県内初の出荷制限一部解除という難問に戸惑っていた町役場もより積極的になり、解除を勝ち取った。さらに町は処理施設建設の半額を負担した。それでも総事業費の8割以上をK氏が融資により賄って事業はスタートした。
MOMIJI成功の要因
その後、MOMIJIのシカ肉販売は成功を収めるが、その要因として次の3点が指摘できる。①震災復興と結びついた共感を呼ぶシカ肉販売のストーリー性②少人数で捕獲・加工・販売まで担うリーズナブルなビジネス形態③他地域のシカ肉とは一線を画する味の良さである。特に③についてみれば、肉質の柔らかな3歳以下のオスと4歳以下のメスをストレスを与えずに仕留め、直後に血抜し、捕獲後1時間以内に加工施設へ持ち込むという条件を満たした高品質なシカ肉のみが提供されている。共感できるストーリーを帯びた美味しいシカ肉が低コストで提供されれば成功は自明であろう。23年4月には、加工施設が新設され、これまでの3倍以上の出荷が可能となり、K氏の決断と努力は報われつつある。
被災地におけるジビエ利用と汚染者負担原則
野生鳥獣問題解決に向けた取り組みにも原発事故は悪影響を与えた。MOMIJIがそれを突破できたのは、地元の暮らしを大切に思う経営者の熱意や工夫とそれを支えた関係者との社会関係資本の存在だった。全国的にも成功例の少ないジビエ事業をビジネスとして成功させたさまざまな工夫は全国的な課題解決に一般化できるものであり、関係者の皆様に深く敬意を表する。同時に原発事故影響によるマイナスをゼロに戻すための努力を直接ジビエ事業に振り向けられれば、関係者の苦労はどれだけ軽減されただろうかという思いも脳裏を離れない。こうした地元関係者の努力の中に原発事故被害解消を紛れ込ませるのでなく、汚染者負担原則に基づいて原因者こそが取り組むべきではないのだろうか。
事故影響に悩む地域は今も残されている。