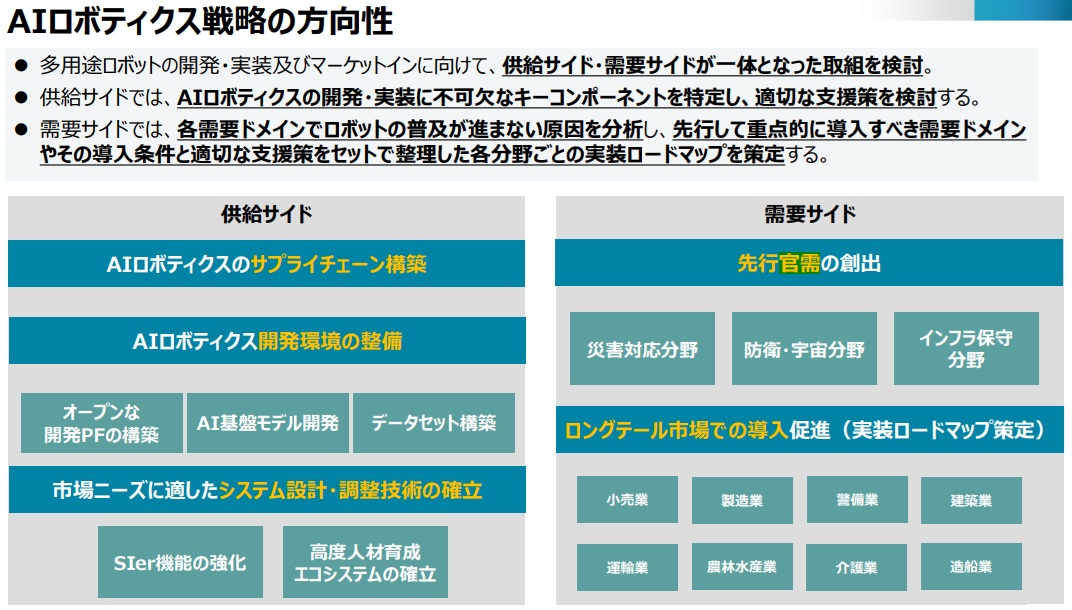西村経産相、防衛産業の基盤強化を表明 中小企業の供給網整備、軍民両用化も
西村康稔経済産業相は、年末の国家安全保障戦略など安保関連3文書の改定へ向けて防衛産業の基盤強化を図る方針を表明した。中小企業を含めた防衛装備品のサプライチェーンの維持強化、科学技術の軍民両用化を図る。政府の有識者会議は9月30日、防衛力強化のため法人税増税など財源確保策の検討を始めた。脱炭素をエンジンとした経済成長の財源は炭素税などカーボンプライシング(CP、炭素の価格付け)で賄う方針だ。(小峰純)
★「軍需省」は否定
9月13日。西村康稔経済産業相は閣議後記者会見で本紙記者から問われた。
「日本有事に直結する台湾有事に備えて、経産省の体制整備をどう図っていくつもりか。弾薬不足、航空機や戦車の稼働率の極端な低下など、日本の継戦能力はあまりにも脆弱だ。またAI(人工知能)や量子といった先端技術やドローン(無人機)といった既存技術の軍民両用化も避けてきた。軍需産業(防衛産業)こと装備産業の維持・育成に経産省は、サボタージュしてきたツケが回ってきたといっても過言ではない。経産省の名称を「経済・産業・軍需省」に変更するほどの体制整備が西村さんの主導によって期待されているが、どうか」
経産省の前身は「商工省」だが、太平洋戦争中は「軍需省」だった。軍需省は1943年11月1日、勅令に基づき、それまでの商工省の大半と企画院の国家総動員部門を統合して設置された。だが戦後の進駐軍上陸を目前としていた45年8月26日、当時の椎名悦三郎次官らの指導により終戦の同15日から10日間余の徹夜の作業によって勅令に基づき、商工省に名称を戻した経緯がある。軍需省のままだったら内務省のように、GHQ(連合国軍総司令部)に解体され、今の経産省はなかったかもしれない。その分、防衛産業の維持・育成にそれまで手を抜いてきた。しかし時代は変わり、いま防衛産業の育成は経産省にとって待ったなしの最重要課題といってもよいだろう。
西村経産相は「なかなか大胆な質問をいただき、ありがとう」と述べた上で「防衛産業を所管している立場として、それに関わる中小企業政策も含め防衛産業のサプライチェーン(供給網)の維持強化、デュアルユース(軍民両用化)技術の促進に取り組んでいる。今後も昨今の安全保障環境を見て、さらに力を入れて取り組んでいく意を強くしている。防衛省との連携を深めていきたい」と防衛産業の基盤強化に取り組む姿勢を強調した。ただ名称変更については否定した。
★「共食い」の装備品
ロシアの侵略に対し、ウクライナの徹底抗戦は半年を超え、さらに長期化する見通しだ。ウクライナ軍の抗戦能力は士気の高さのほか、欧米からの武器支援によるところが大きいが、継戦能力の維持にも日頃から努めてきたからだとされる。
しかし、日本の自衛隊の継戦能力はあまりに貧弱だ。防衛省によると、備蓄するミサイルや弾薬は、戦い方にもよるが、有事に1週間から数カ月しか持たないという。その窮状の示す言葉が「共食い」だ。戦闘機や哨戒機、護衛艦、戦車など多岐にわたる装備品分野で日常的に行われている。装備品の維持整備費の予算不足で部品が確保できない際、同型の装備品から部品を外して流用し、当座をしのぐ手法だ。部品を抜かれた装備品は使い物にならないため、同省の調査によると、装備品の稼働率は5割強にとどまるという。
なお「継戦能力」の確保は抑止力の向上にもつながる。相手国に抗戦が長期間続くと思わせれば、侵攻を踏みとどまらせることもできるからだ。
継戦能力の貧弱さには、経産省の責任も大きい。日本の防衛産業の衰退傾向に歯止めをかけてこなかったからだ。防衛省によると、ここ20年間で、防衛分野から撤退した企業は100社を超えるという。大手企業でも小松製作所や住友重機械工業が機関銃など一部装備品からの撤退の意向を表明している。大手企業の撤退は中小の関連企業約1万社にも影響を与える。技術継承は国難になり、弾薬の増産や装備品の整備の担い手が減少し、継戦能力を脅かす。放置すれば、防衛産業は存続の危機を迎え、国防に重大な影響を与えかねない。
防衛産業の基盤強化のためには、装備品の海外移転も欠かせない。納入先が自衛隊にとどまる限り、単価がかさむ少量製造という問題の抜本的な改善が見込めないからだ。「防衛装備品移転3原則」の見直しが必要だ。また政府全体で年4兆円を超す科学技術関係予算の防衛分野での有効活用として軍民両用化も欠かせない。
★当面は「つなぎ国債」
政府は9月30日、防衛力強化に向けた「国力としての防衛力を総合的に考える有識者会議(座長=佐々江賢一郎元外務次官)」の初会合を首相官邸で開いた。会議では「反撃能力」(敵基地攻撃能力)の保有や防衛費の国内総生産(GDP)比2%を目指した財源確保策などを検討し、年末までに予定する「国家安全保障戦略」など安保関連3文書の改定に反映させる。政府内には、財源確保で法人税増税案が浮上している。当面は「つなぎ国債」でしのぐ案だ。
一方、脱炭素をエンジンとした経済成長のためには、炭素税や排出量取引によるカーボンプライシング(CP、炭素の価格付け)収入が入るまで「つなぎ国債」として、「脱炭素国債」こと「GX(グリーントランスフォーメーション)経済移行債」の発行が検討されている。


![[AD]BitNavigator_850_150](https://www.kankyo-news.co.jp/uploads/2026/02/17/rDUhxjfMQSzbhbshHqyA1FTfIUpHL4M0kLVTi6Ru.jpg)