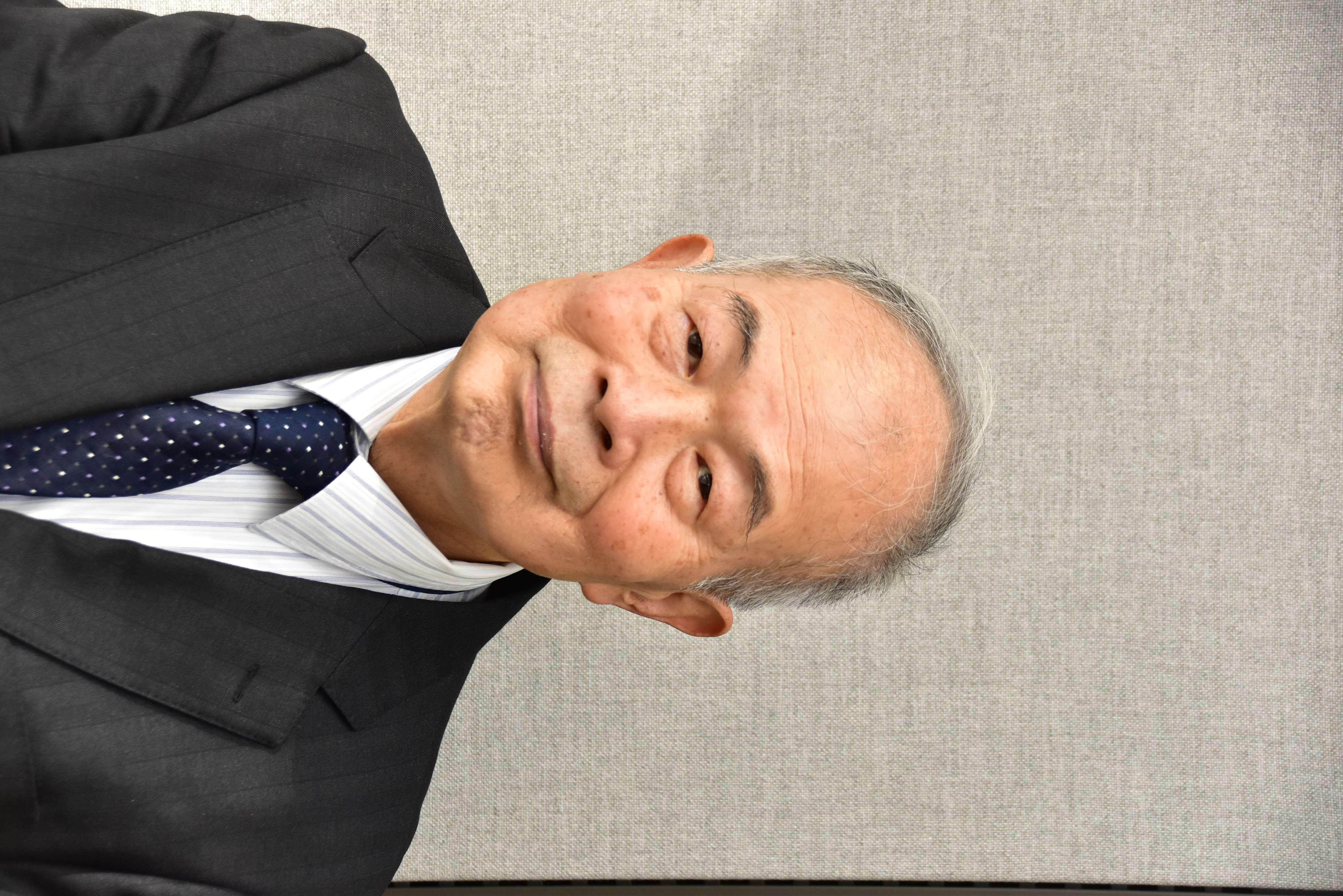オルタナティブ・テクノロジー(54) 超高温好気性発酵システム 有機物を自然に還し、農業振興で地方創生(その2) 吉村俊治社長に聞く
前回に引き続き、YM菌という微生物を活用した超高温好気性発酵システムについて、共和化工の吉村俊治社長に伺います。今回は、日本で最初に国土交通省の補助によるDBO堆肥化事業となった佐賀市の下水汚泥堆肥化事業と、新開発の密閉型撹拌式堆肥化装置「YMひまわりくん」を紹介します。
――下水道展にあった佐賀市の下水汚泥堆肥化事業について伺います。
この事業は佐賀市が全国で初めて、国土交通省の補助金を頂いた、DBO方式の堆肥化施設です。当社は地元建設会社とJVで施設をつくり、山有(鹿児島県)、地元企業と共同でこの事業の維持管理運営を担う特別目的会社を設立し運営しています。
事業化に当たり苦心したのは汚泥の性状です。バイオガス抽出後の消化汚泥は、エネルギーを取った分、生汚泥より栄養分が少なく、難分解性の物質が多く残っています。これを何とか乗り越えて、優れた発酵肥料とすることができました。化学肥料や農薬の多用で疲れた土壌を生き返らせ、安全安心な農業生産の一翼を担っていきたいと考えています。
下水由来の肥料には、肥料の三要素の窒素とリン酸を豊富に含み、また他の肥料にない人体由来のミネラル分を含む特徴があります。我々が生産する堆肥には微生物が豊富に含まれており、植物の根圏で共生関係を築くエンドファイトが生じます。これにより、植物の免疫機能や生長機能を向上させることができるとされています。
――下水汚泥だけよりも、混合バイオマスの方が苦労は少ないということですね。
混合バイオマスの方が、窒素、リン酸、カリのバランスがよいことは確かです。先に申し上げたように河川堤防の刈草を汚泥と混ぜればカリが補給されより良い堆肥になります。国交省には是非ともご検討して頂きたいものです。
――さすがに環境と農業の先進市として知られる佐賀市ならではの好循環と思いますが、全国的な販売のご苦労はありますか。
当社の堆肥は全て農林水産省の肥料登録を受けていますが、農協が拒否反応を示して出口が詰まったことはありました。最終的に、佐賀市では処理場内にてセルフサービス方式で販売することで安価に提供しており、毎年1400㌧が完売しています。
――自分の売る肥料のライバルと考えたのか、困ったものです。こんな障害がある場合、口に入らなければ文句はあるまい、エネルギー作物に施肥するというお考えはありますか。
ベトナムからジャトロファに施肥できないか引き合いはあります。
――次に、いま普及に注力している「YMひまわりくん」について伺います。
YMひまわりくんは、超高温好気性発酵システムをコンパクトな円筒に押し込み、外胴の回転で撹拌する密閉型撹拌方式堆肥化装置です。堆肥化後、養生槽で熟成させると、さらに上質の堆肥になります。
沖縄県の金武町から北海道まで全国13カ所で展開しています。
親技術と同じく守備範囲の広さが特徴で、下水汚泥、農業集落排水汚泥、し尿汚泥、生ごみなど多様な物質を処理します。
導入先では、環境と土壌を守るさまざまな運動が生まれてきています。栃木県益子町では、堆肥化するために、生分解性プラスチックのごみ袋を導入する等新たな動きもあります。
――資源化の遅れているし尿汚泥の処理、生ごみ分別による焼却炉火力アップなど、周辺にもいい影響をもたらしているようですね。地域からの脱炭素という運動で、最近の目立った動きはありますか。
滋賀県の琵琶湖流域下水道高島浄化センターの汚泥の堆肥化事業を受注しています。今年から建設工事に着手しており、来年度中の供用開始が予定されています。着工までには紆余曲折がありましたが、当社の提案が採択されました。
あとがき
すばらしい技術について、思う存分語っていただき、楽しい取材でした。有機物の物質循環による土壌再生、食物の自給率向上にさらなる発展を期待します。
下水道アドバイザー 神林 章元