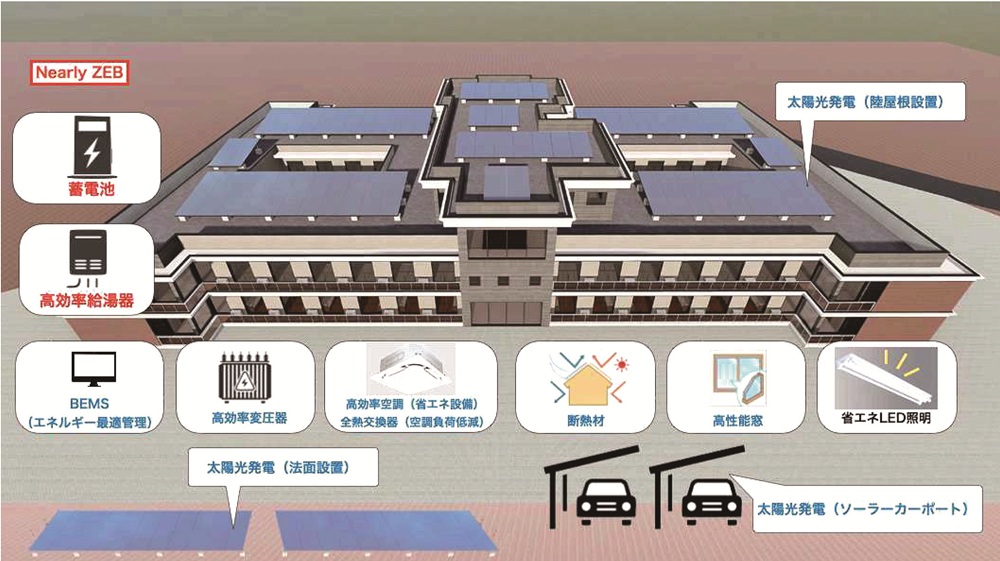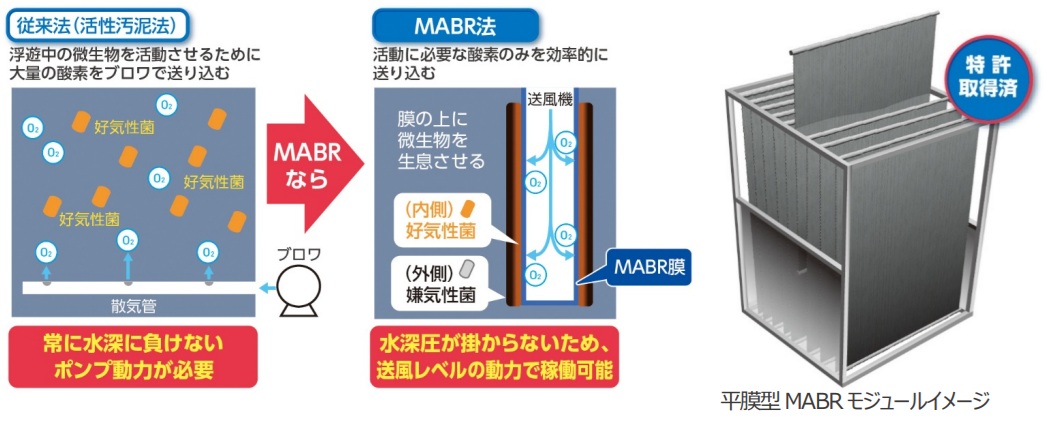プランテック 代表取締役社長 勝井 基明 氏 「マルチフューエル」対応のバーチカル炉で「焼却炉のスタンダード」を目指す
――2023年を振り返って。
昨年は6件の新設プラントの竣工があり非常に忙しく、中身の濃い1年であった。6件のうちの2件はボイラー発電付きの案件であり、1つは茨城県の高萩・北茨城広域事務組合の施設で、自治体向けのバーチカル炉(竪型ストーカ炉)では発電付きの第1号案件となり、当社にとって非常に意味のある竣工案件となった。もう1件は民間の産業廃棄物処理施設で、バーチカル炉では最大の1炉あたり120トンの規模になる。この他に民間の4施設が竣工したが、いずれも順調に稼働しており、改めて当社の技術の確かさを示すことができたと考えている。最近は大型案件の引き合いも多く、中・小型から大型までの実績ができ、自治体案件でも発電付き施設が稼働し、その長期包括運営業務も請け負い、建設・運営共に実績ができたので、今後に向けて弾みがついたと手応えを感じているところだ。

――燃料や資源の高騰等厳しい環境だったが。
コストが予想以上にかかって厳しい状況ではあったが、それでも操業以来連続の黒字を確保することができた。
――課題は。
当社に限ったことではないとは思うが、人材確保が大きな問題となっている。当社としては新卒採用よりも、即戦力となる技術者や有資格者のキャリア採用が2024年問題や関西万博の影響もあり非常に厳しい状況である。そうした状況下で環境業界各社だけでなく建設業界等、広い範囲で人材の囲い込みや取り合いの状況になっているようである。
――技術開発等の取り組みは。
9件の大学等との共同研究を行っており、これらは今後も継続していく予定だ。環境プラント業界ではAIによる自動運転等に注力する動きが目立っている。当社としても当然ながら、AIの有効活用について検討しているが、まずはそうしたものに頼らなくても炉自体の根幹の技術を磨くことによって、人手をかけずに安定的な焼却を実現することを重視している。バーチカル炉は、焼却炉自体の付加価値が高いと考えているので、この技術解析や理論分析などには引き続き力を入れていきたいと考えている。
――カーボンニュートラル等社会課題への貢献は。
自治体向けの発電付きバーチカル炉の実績もできたので、脱炭素の対応としてエネルギー利活用案件には積極的に取り組んでいく考えだ。また、バーチカル炉の特徴を生かし、地域から出る汚泥なども廃棄物と合わせて処理することができるので、別々に処理していたものを1つの施設で処理することで燃料の削減にもつながり、汚泥処理の際に発生するN2Oの削減も実現できる。こうした面でもカーボンニュートラルに貢献可能である。一般廃棄物、産業廃棄物、医療廃棄物、災害廃棄物、汚泥などさまざまな廃棄物に広く対応できるバーチカル炉(竪型ストーカ炉)を「マルチフューエル」に対応する焼却炉として、自治体向け、公民連携を含む民間向けに拡販していき、地域に大きく貢献していきたいと考えている。
――海外での展開は。
海外では、コロナ以降中止されていた展示会なども徐々に再開して来ているので、そうしたところに出展するなどで認知度向上を目指しているところだ。メディアでは海外で焼却炉の引き合いが旺盛になっているといった報道も目にするが、まだそれほど動きが出ているとは感じていない。形になるまでにはもう少し時間がかかるのではないかと見ている。ただ、医療廃棄物の処理などのニーズがあることは確かなので、そうしたニーズを着実に掴んでいき、その国・地域の焼却炉第1号がバーチカル炉というケースを増やしていきたいと思っている。
――今年の展望や今後の目標は。
まずは人材確保が課題となっているので、人材を確保し、育成、ケアして行けるように組織体制を整備していくことに力を入れていく。また、バーチカル炉のさらなるブラッシュアップを目指して技術解析を進めていく。今後さらにDX化や図面の3D化も広げていき、社内の技術整備につなげていきたい。将来的な目標としては、バーチカル炉を焼却炉のスタンダードにしていきたいと考えている。廃棄物を燃やすことを目的に開発された唯一の炉であり、廃棄物処理には最も適していると自負している。「世界のスタンダード」と「マルチフューエル」の2つをキーワードに、今後もさらなる進化を目指していく。