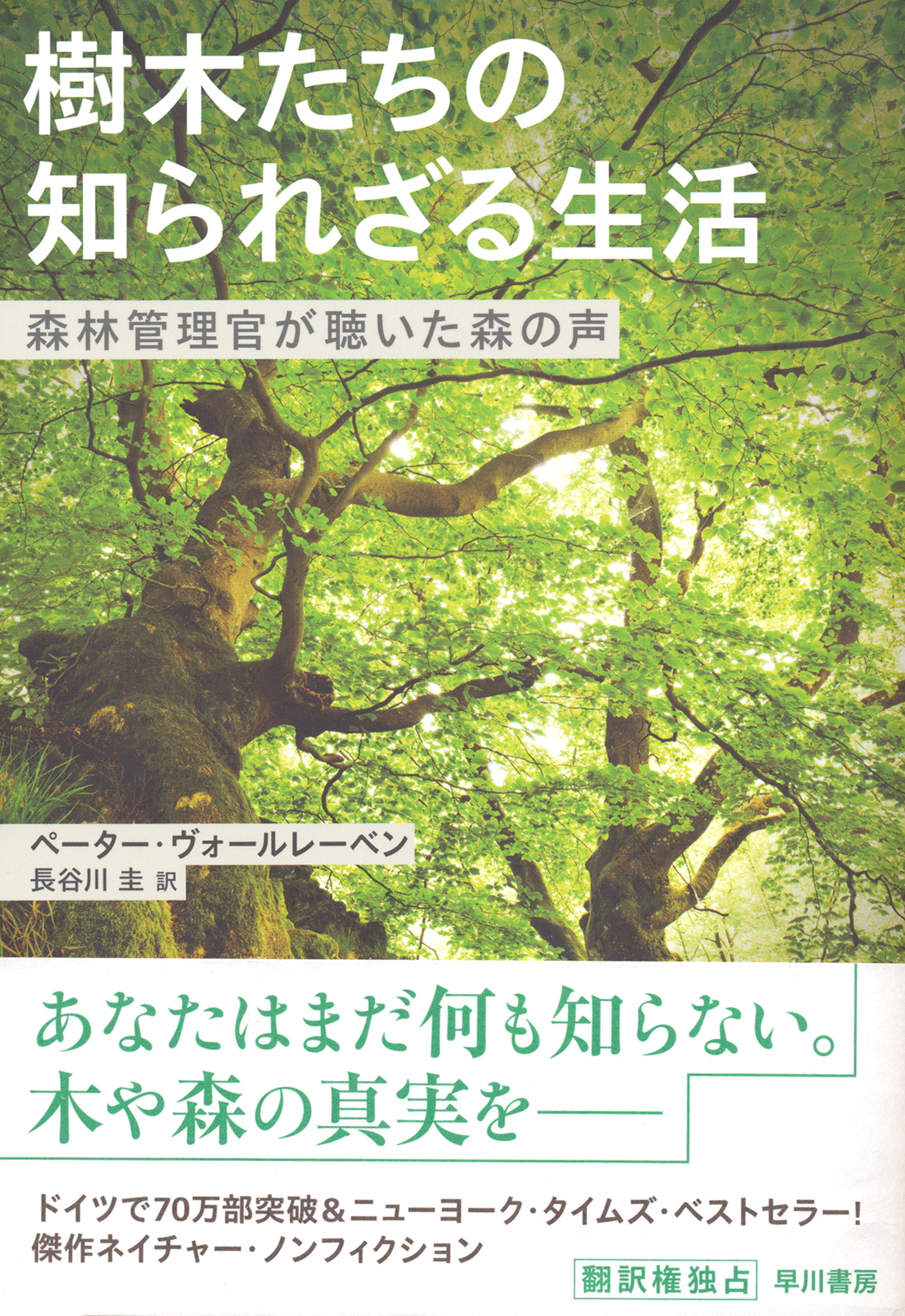街路樹ものがたり(48) ドラマ『サイレント』と樹木の会話
ドラマ『サイレント』(脚本・生方美久)は、昨年10月から12月にフジテレビで放映され、大人気を博しました。若者の恋愛ストーリーに、聴力障害という珍しい要素を加え、コミュニケーションを主題としました。優れた脚本に、映像と音楽の美しさも加わり、私も夢中になりました。
題材の一つは、難聴や失聴の障害を持つ人の悩みや、社会的課題です。
もう一つは、コミュニケーションの多彩な手段です。会話の外、手話、読唇、ゼスチャー、筆談、音声変換アプリやメッセージアプリ、プレゼント、メッセンジャーとしてのポピュラー音楽、和歌、詩等が描かれます。最終回では「花には音がないけど言葉がある」として花言葉も取り上げます。看護師でもある作者の表現鮮やかな力作です。
非言語的コミュニケーションといえば、私は樹木の意思疎通を考えます。2015年ドイツで書かれた『樹木たちの知られざる生活:森林管理官が聴いた森の声』(邦題)は、営林署の職員だった著者が、人間本位の林業ではなく、樹木の生態に即した森林保護をするために職を辞し、フリーの営林者になり、著したそうです。樹木の素晴らしい生き様を擬人的に説明し、樹木への愛にあふれ、読者の胸を打ちます。
「木の言葉」として紹介される例として、アフリカ・サバンナのアカシアは、捕食者のキリンがくると、数分以内に葉の中に有毒物質を集め、エチレンガスを発散して周りの木に警告すること。毒に気づいたキリンは別の木に移動する、警告を受けた木も有毒物質を準備するそうです。
木の根は、時に樹冠の倍以上の大きさに広がりますが、実は周りの木と地中で接し、菌類が媒介して、情報伝達をする、インターネットの光ファイバー網のようなネットワークを形成するそうです。
衰弱した木が害虫に攻撃されるのは、周囲の木との伝達能力が失われたからだそうです。
つまり樹木は、香りと視覚と(根の先端で交換する)電気などを使って会話する、そして周囲の仲間同士が協力し合い、上部を伐られた切り株や、養分が足りない木に養分を融通し、若い木に伸び方を教え、コミュニティ(森)全体として生きるというのです。さらに樹木には、記憶や痛みもあるといいます。
この本は世界で100万部以上を売り上げ、34カ国で翻訳されたそうです。この後、樹木のメッセージや恩恵に注目した著作が相次ぎました。他方、ドラマ『サイレント』は週に1千万回を超える再生を記録したそうです。
これらの作品は、コミュニケーションに苦慮する「コミ障」の時代の救いであり、助け合うことを教えてくれます。両方の作者が、樹木医と看護師という医療者であることも印象的です。都市化、複雑化、IT化、競争化する世界で、自然から離れ、孤独と五里霧中に病む私たちにとって、、樹木たちが治療者となるように思います。
一般社団法人 街路樹を守る会 代表(共立女子大学他 非常勤講師)愛 みち子